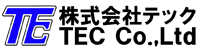 ハードウェアの設計・開発業務のテック
ハードウェアの設計・開発業務のテック
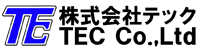 ハードウェアの設計・開発業務のテック
ハードウェアの設計・開発業務のテック
シリアル転送方式のインターフェイスの規格のこと。パソコンと周辺機器を簡単に接続できる。周辺機器へ電源の供給も可能。
ほとんどのパソコンに標準搭載されている、シリアル通信規格。信号線の目的やタイミング、接続コネクタも規定されている。(D-SUB 25ピンまたはD-SUB 9ピン)
電子・電気機器における特定有害物質の使用制限について欧州連合から出された指令。
有害物質として指定された、鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニール(PBB)、ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE)が、規定値以上含まれている製品を欧州で販売する事が制限されている。
RoHS対応の工場にて製造しております。
数値制御(NC)による機械加工の事。基板制作においては主に穴あけ加工の事を指す。穴位置や穴径を指示するNC加工用データはNCデータと呼ばれる。
International Organization for Standardization(国際標準化機構)の略。
品質マネジメントについて定めたISO9000、環境マネジメントについて定めたISO14000等の規格があり、認証を得る事で企業の信頼性を高める事が出来る。
ISO9001、ISO14001認定取得工場での製造に対応しております。
Field-Programmable Gate Arrayの略。 製造後に構成を書き換える事が出来る集積回路の事。
専用の集積回路(ASIC)より量産時の単価は高くなるが、開発期間と開発コストを抑えられ、修正や変更が容易となる。
弊社技術者による設計実績があります。
CEM-3 (Composite epoxy material-3) ガラス布・ガラス不織布複合基材エポキシ樹脂銅張積層板。FR-4に比べて、剪断、切削性に優れるため、スルーホールめっき穴以外の丸穴、角穴、複雑な外形などは金型でパンチング加工できる。FR-4と特性がほぼ同等であるため、両面スルーホール板に広く用いられコスト的にもガラスエポキシより安価である。ただし、寸法安定性、機械強度などの点はFR-4に劣るため、多層板では使用しない。
Comparative tracking index(比較トラッキング指数)の略。 絶縁物のトラッキングのおこしにくさを示す値。この値は、絶縁物表面に電圧を印加した状態で 所定の試験液 (通常は塩化アンモニウム 0.1% 水溶液) を滴下させて どの電圧までであればトラッキング破壊を生じないかを調べることによって 判定するものであり、その値が大きければトラッキングを起こしにくいことになる。トラッキングとは、絶縁物の表面での微小放電が繰り返されることによって 絶縁物表面に導電性の経路が生成され、絶縁破壊に至る現象である。 火災の原因になるので電源回路を搭載する基板においては通常CTI値600取得の材料が求められることが多い。
Ball Grid Arrayの略。底面に小さなボール状の電極が整列している部品。数十~数千ピンのICを小さな面積で実装する事が出来る。
1000ピンを超える多ピンBGAの設計、
0.4mmの狭ピッチBGAの実装実績があります。
Blind Via Holeの略 プリント配線板の外層と内層を層間で接続する為の穴。貫通していない形状の穴。
一段ビルド,二段ビルドの設計実績があります
Computer Aided Design(コンピュータ支援設計)の略。
コンピュータを用いて設計、製図をする事。またはそのための設計支援ツール。
電気用CADとして、回路設計CADと基板設計CADがある。
保有CAD
PWS :4ライセンス
Board Desiner :3ライセンス
D-Force :2ライセンス
Design Gataway:1ライセンス
OrCAD :1ライセンス
Computer Aided Manufacturing(コンピュータ支援製造)の略。
CADで制作されたデータを用いた製造システムの事。
Central Processing Unit(中央演算処理装置)の略。コンピュータにおいて中心的な処理装置として働く電子回路の事。
Design Rule Checkの略。基板設計のデータが設計規則に違反していないかを検証する事。
CADツールによって機械的に検証を行うことが出来る。
DRCをONにしエラーにならない設定で設計しています。
Electro Magnetic Compatibility(電磁両立性)の略。
電子機器から発生する電気的ノイズ(EMI)と他の電子機器から受けるノイズ(EMS)を抑え、電磁的な不干渉性と耐性を備える事。
ノイズによる電子機器の誤作動や、電磁波による人体への影響を抑えるために必要性が高まっている。
Electro Magnetic Interferenceの略。電子機器から発生する電気的なノイズ(主に電磁波)の事。
Electro Magnetic Susceptibilityの略。電子機器が他の機器等の外部から受ける電気的なノイズ(主に電磁波)の事。
Electro Static Discharge(静電気放電)の略。精密な電子部品は静電気で容易に破損してしまうため、部品実装等の作業工程ではESD対策が必要とされている。
Flexible Printed Circuits(フレキシブルプリント回路)の略。FPC基板。
ポリイミド等の絶縁性と柔軟性を持った薄い材質に、銅箔等で電気回路をプリントした基板の事。
薄く、曲げる事が可能なため、小型携帯機器内部等の狭い隙間にも配置する事が出来る。
FR-1:プリント基板の基材の一種。耐燃性紙基材フェノール積層板
FR-2:プリント基板の基材の一種。耐燃性紙基材フェノール積層板
FR-3:プリント基板の基材の一種。耐燃性紙基材エポキシ積層板(=紙エポ)
FR-4:プリント基板の基材の一種。耐然性ガラス基材エポキシ樹脂積層板(=ガラエポ)
現在、一番一般的に使われている基材。
Light Emitting Diode(発光ダイオード)の略。ダイオードの一種で、電圧を加えると発光する半導体素子の事。
赤、青、緑のLEDを用いることでフルカラーを表現することが出来る。また、発熱によるエネルギー消費の大きい電球に代わる照明器具として普及が進んでいる。
Large Scale Integration(大規模集積回路)の略。集積回路(IC)の中でも特に素子の集積度が高い大規模の集積回路の事を指すが、ICと同義で用いられる事も多い。
Micro Processor Unit(小型演算処理装置)の略。コンピュータの演算処理を担う半導体チップの事。CPUとほぼ同義で用いられる。
Printed Circuit Board(プリント回路基板)の略。部品が実装された基板の事。実装前の基板でもPCBと呼ばれる事もある。
Printed Wiring Board(プリント配線基板)の略。部品実装前の基板の事。
アメリカの安全機関UL社の認証マーク。製品の安全性を定めた規格を満たした製品にのみ認証マークの使用が認められるため、基板等に表記することで製品の信頼性を示す事が出来る。
基板の層間を導通させるための穴。
スルーホールの中でも部品のリードを挿さない導通用の穴を指してVIAと呼ばれる場合がある。
プリント基板の表面にV字の溝を掘ることで、折り曲げて分離出来るようにする加工の事。
主に抵抗やダイオード等で、円筒形の両側からリードが出ているの部品。専用の加工機等でリードを折り曲げて基板に実装する。
回路図を元に、部品レイアウト・配線パターン図作成を行い、基板製造用のデータを作成する工程の事。基板設計、パターン設計とも呼ばれる。
基板にあける穴の直径の事。
スルーホールの場合は穴の内側にメッキ処理が施されるため、加工に使用するドリルの直径よりも若干狭くなるので、ドリル径、仕上がり径等と区別する場合がある。
銅箔のない絶縁基板に無電解銅めっきを主体として導体パターンを形成するプリント基板の製法。
連続的に変化する電気信号を取り扱う電気回路の事。対するデジタル回路に比べてノイズに弱く設計も難しい。
内層間にめっきされたスルーホール(ITHやIVHと略する)。外層にランドが無い為、配線や部品配置領域が広がる。
IVHの設計実績有ります
交流回路における電圧と電流の比。交流抵抗値。
銅張積層板やプリント基板の銅の不要な部分を化学反応で溶解除去し、所要の導体パターンを形成すること。
絶縁物の表面に沿って測定した2つの最短距離。
電線をらせん状に巻いた電子部品(=インダクタ)。ノイズ除去回路や共振回路などに使用される。
ペースト状の半田で面実装に使用されます。半田の粉末にフラックスを加えて適当な粘度にした物です。面実装工程で電子部品の半田付け部分に印刷して使用します。近年は環境対応の観点から鉛フリー金属組成(主にSn-Ag-Cu系)が広く使用されております。
一般的な鉛フリー半田(Sn-Ag-Cu系)では銀の含有料は約3%ですが材料価格の半分近くを銀が占めます。銀レス半田は一般的に銀を含まない、もしくは1%以下程度の含有量の低銀半田のことです。近年は接合信頼性、はんだ濡れ性もSn-Ag-Cu系とほぼ同等に改善されコストダウンの為、使用されるようになりました。
基板の表面処理方法のひとつ。基板表面の銅箔に下地としてニッケルめっきを施しその上に薄い無電解金めっきをする。
接触面の電気抵抗が小さく、酸化・腐食防止に優れていて保存性が高い。
めっき厚が薄く剥がれ易いため、抜き差しの多いエッジコネクタ等には金フラッシュではなく、めっき厚を調節できる電解金めっきを用いる。
Gerber Format(ガーバーフォーマット)形式で作成された、基板製造用データの事。
旧式の標準ガーバー(RS-274D)と、拡張ガーバー(RS-274X)が一般的に使用されている。
標準ガーバーには形状データが含まれないため、別途アパーチャーリスト(Dコード表)を用意する必要がある。
共に出力対応しています
多層プリント配線版の外層に形成するパターンの事。
電気回路を構成する、導線以外の要素の事。抵抗、コンデンサー、トランジスタ等。
片面にのみ導体パターンが存在する基板。最近はあまりないです。
電子部品や電子回路の電気的な方向(+端子、-端子等に対して、正しい電位を印加する必要がある
例:発光ダイオード(LED)のカソードには電位のマイナス側(電位の低い側)、アノードには電位のプラス側(電位の高い側)を印加する
多層プリント配線板の内層に、グランド電位にするための大地への接続、電源の供給などのために設けた導体層。
内層のいくつかの層を電源層とグランド層とし、シールドの役目もはたしている。
多層板の内層導体パターンとスル―ホールとを導通させない為にスル―ホールの周りの導体をなくした領域の事
電気を蓄える性質をもった素子。電流を安定させる事が出来る。
交流を直流に変換する仕組の一部になくてはならない素子(部品)です
コンピュータ等のシステムにおけるプログラム等の処理を行う物を指し、機械、装置、設備等のハードウェアを制御するため等に用いられる。 ⇔ハードウェア
基板にドリルで穴をあけた際に生じる溶けた樹脂のかす。
そのまま穴をメッキ処理すると不良の原因になるのでスミアを取り除く作業をデスミアと言う。
水晶の特性を利用し、周波数精度の高い発振を起こす際に用いられる素子の一つ(=Xtal)。
データの転送方式のひとつで、データを1ビットずつ連続的に転送するしくみ。少ない信号線で接続が可能。RS-232C、USBなどがある。
パターンの末端における信号の不要反射を防ぐためにつけられる抵抗。
1つの信号当たり必ず2本の信号が使われ、2つの信号の電位差が信号レベルになる。2本にノイズがのっても相殺されるため、ノイズに強い。
金属張絶縁基板不の導体箔の不要部分を、エッチングなどにより、部分的に除去して導体パターンを形成するプリント配線板の製法。
ベタパターン上など熱が逃げやすい箇所にランドを設置する場合、ハンダ付け時の温度低下を防ぐ目的のランド。
ベタパターンへ接続するパターンの面積を減らすことで熱の放出を抑える。
コンピュ-ターを利用して現実に想定される条件を入れて実際に近い状況を作りだす事。模擬実験
伝送線路のシミュレーションの実勢があります
抵抗、コンデンサ、トランジスタ等複数の回路素子を一つにまとめた電子部品の事。
集積する素子数の規模によってSSI、MSI、LSI、VLSI、ULSI等に分類されていたが、近年では集積度の高いものは総じてLSIと呼ばれる。
部品番号や回路記号等をプリント基板表面に印刷する。
主に白色シルクの対応しています。
多層プリント配線板で、主に信号の伝達をする信号線の導体パターンがある層。
基板の層間を導通させるための穴。穴の内側にメッキを施して層間を接続する。
交流を直流に変換する事
抵抗する、耐えるという意味が有り、ほこりや熱、湿度などから回路を保護すると同時に絶縁体としての機能があります
実績レジスト色は,緑色,青色,赤色,白色の実績が有ります
主に、複数のコイルを同じ磁心に巻いたもので、電圧変換の機能を有する。交流電圧を降圧もしくは昇圧させる為に使用する。
信号を増幅、または回路をオン、オフさせる半導体素子。たとえば、NPNやPNPの順番で半導体を挟む構造がある。
配線を形成する銅箔の厚み 一般的に35um(外層) 18um(内層)
表面実装部品をプリント基板に配置する装置。これにより大量の部品を自動的に配置する事が出来る。
1方向のみに電流を流すことができる(整流作用)電子素子。この特性を利用し、主に電源回路や保護回路などに用いられる。
通常4層以上の配線層を持ち、ウエハース状に絶縁体とパターンを積み重ねた基板。片面や両面では収容しきれない回路配線を層を増やすことで対応する。表面以外の層は目視で確認できないため保守性は劣る。
実績層構成:4層~10層の実績が有ります
配線と、部品ピンもしくはVIAとの接続を確実にするために付加する涙状のランド。
お客様のご要望により対応実績が有ります
電気を流れにくくする部品で流れる電気の量を制限したりする事で電子回路を適正に動作させる大切な部品です
電気信号を電圧の高さで2つの信号に区別して扱う電気回路の事。信号をHighとLow2種のみで識別するためノイズの影響を受けにくい。
プリント基板の導体層のうちで、電源を供給するために使用する層のこと。
電子部品を電気伝導体で接続し電流の通り道をつくり、目的の動作を行わせる電気回路のこと。
伝藩媒体を用いて交流電気エネルギーを伝達する時に伝藩媒体中に発生する電圧と電流、または電界と磁界の比のこと。
シングル50,75,差動90,100Ωの設計実績が有ります
電気の流れをコントロールする部品です
鉛をほとんど含まない無鉛はんだの事。RoHS指令により人体に有害な鉛等の電子機器への使用が制限された事等で普及が進められている。
通常のはんだより高温で扱う必要があるため、使用機器等を鉛フリーはんだに対応させなければならない。
鉛フリーはんだでの制作に対応しております。
多層プリント配線版の内層に形成するパターンのこと。
6層基板,8層基板,10層基板での内層パターン配線実績有りがあります
支給して頂いたネットデータと、設計データからの逆ネットを比較し、相違がある場合はどこが違うのかなどを検証する。
設計全案件にお客様の支給ネットを元に実施しています
媒質中により温度勾配がある場合にその勾配に沿って運ばれる熱流束の大きさを規定する量のこと。
電子回路における端子間の接続情報のデータのことである。
主にTelesis,PADS,Tangoでの支給実績です
穴内側をメッキせず電気的に接続されていない穴のこと。
プリント基板内部の水分を蒸発させるために基板を加熱する処理の事。 基板の反り、基材となる樹脂部分、銅配線、レジストの層が剥離してしまう現象を防ぐ為。
プリント配線板の設計および製造の技能を認定する国家資格。設計作業と製造作業に区分されている。
既定の実務経験年数と学科・実技試験に合格する事で取得できる。
弊社では、設計作業1級:1名、2級:3名、3級:1名 取得済みです。
基板の表面処理方法のひとつ。基板の銅箔表面に防錆皮膜を張るフラックスの事。はんだ濡れ性が上がるため、実装作業の効率が良くなる。
部品をはんだ付けする際に、酸化膜の除去と表面張力を低下させてはんだ付けをしやすくする効果がある。
実装時に塗布して使用したり、はんだ自体にも含まれている。
プリント基板をオープン/ショートテストによって電気的に検査する装置
両面部品実装の基板が多くなっているが、一般的に基板の表側の面の事。設計は基本的に全層を部品面側から透視した部品面視で作業を行う。 ⇔半田面
プリント基板表面に置いた状態でハンダ付けする部品。 メタルマスクを使用する ⇔リード部品
シリコンやゲルマニウム等、電気を通す導体と電気を通さない絶縁体の中間の性質を持つ物質。
この性質を利用して電子の流れを制御する事が出来るため、トランジスタやIC等の電子部品の素材として幅広く用いられている。
両面部品実装の基板が多くなっているが、本来は部品が載らない基板裏面側の事。 ⇔部品面
ハロゲンとは元素で、フッ素(F)、塩素(Cl)、臭素(Br)、ヨウ素(I)、アスタチン(At)の5個の元素のことです。電気電子業界でのハロゲンフリーの定義は明確に決まっていないようですがハロゲンが含有されていない、もしくは意図的に使用されていないことと解釈されています。近年はプリント基板にハロゲンフリー対応品を求めるメーカーが増えています。ハロゲンフリー材は銅張積層板を対象とした規格JPCA-ES01があり5元素の含有限界濃度が規定されています。
外周器。小さな回路素子を包む樹脂や金属等の外形の事。外部からの衝撃や熱などから保護し、実装に適した形状にしている。
システムにおける物理的な構成要素の事。機械、装置、設備等の事を指し、プリント基板もハードウェアにあたる。 ⇔ソフトウェア
伝送線路を組み合わせて作られた特殊な特性をもつ回路。
バイパスコンデンサの略。
トランジスタやIC等の消費電流が一定ではない部品の直近にコンデンサを接続することで、供給される電源電圧を安定させる役割を持つ。
コアとなる基板の上に、薄い絶縁層と導体層を順に積み上げる工法で作成した基板。
プリント配線板の外層と内層との層間を接続するための穴(BTHやBVHと略する)。貫通していないので他の配線、逆面の配置領域が広がる。
4層,6層,8層の設計実績があります
プリント配線と、プリント部品及び(又は)搭載部品とから構成される回路。
溶融ハンダ槽表面に部品を取り付けたプリント配線板を接触させることにより、一括してはんだ付けする方法。
電極バッドの付いた裸の半導体チップのこと。
GNDや電源、大電流のパターンなど、大面積を塗りつぶすような銅箔パターン。
電流容量により対応しています
基板端面の角を無くす事
表面実装部品のリフロー半田付けの際に、ペースト状のハンダを任意の位置に塗布するためのマスク板。
プリント基板の切り離しが出来るように、ドリルの穴を並べてカットしやすくする加工。
高湿中で回路を動作させた場合など、付着した水分で電極がイオン化し、+の電極と-の電極が電気的にショートしてしまう現象で、誤動作や故障につながる。
電位差のある電極同士に十分なクリアランスをもたせるか、防湿剤を塗るなどして対策する。
1枚のプリント基板に複数のアート―ワークを設け、プリント基板完成後または実装後にきり離す方法。
ガーバー出力時に面付け出力対応をしています
プリント基板製作前の試作などに使う基板
弊社では積極的に受託中です。 御相談承ります。
部品の端子にリードが付いていて、プリント基板に空けたスルーホール部に差し込んでハンダ付けするタイプの部品。
柔軟性のない絶縁基材を用いた通常の基板の事。 ⇔フレキシブル基板(FPC基板)
主にコンデンサやトランジスタ等で、片側からのみリードが出ている部品の事
電子部品のピンをハンダ付けする部分。リード部品の場合は穴の開いたランドになる。
表面実装において、あらかじめ端子または電極にはんだをコーティングした部品をプリント板のパターン銅に密着させ、はんだを再溶させて部品をはんだ付けする方法。
両面に導体パターンが存在する基板。
主に電源基板,アナログ基板で設計対応実績があります
半導体チップの入出力ピンの接続方法の1つ。チップのパッドと外部接続パッド間を金等の金属線を溶接して接続する方法。